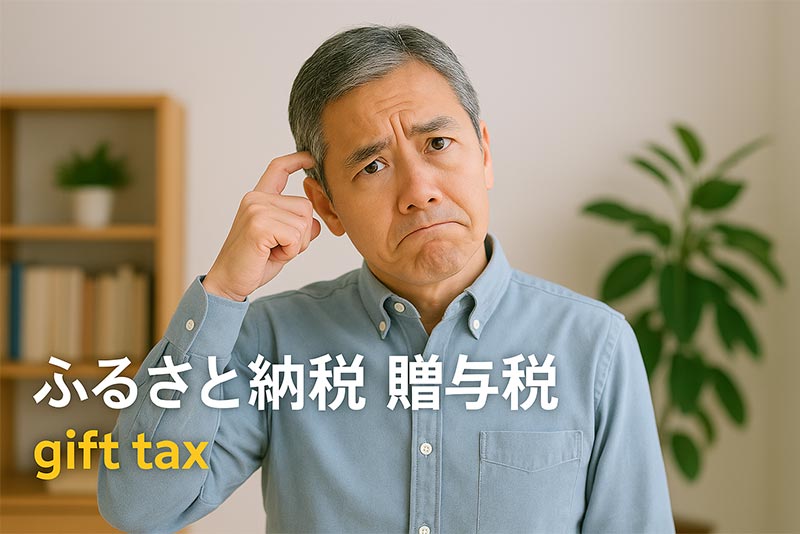目次
※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
ふるさと納税は、自治体への寄附を通じて返礼品がもらえる制度として広く利用されています。
その一方で、返礼品を家族や第三者に渡した際に「贈与税がかかるのではないか」と不安に感じる人も増えています。
本記事では、ふるさと納税と贈与税の関係にフォーカスし、安心して制度を活用するためのポイントをわかりやすく解説します。
ふるさと納税の返礼品を家族と共有すると贈与税がかかるのか
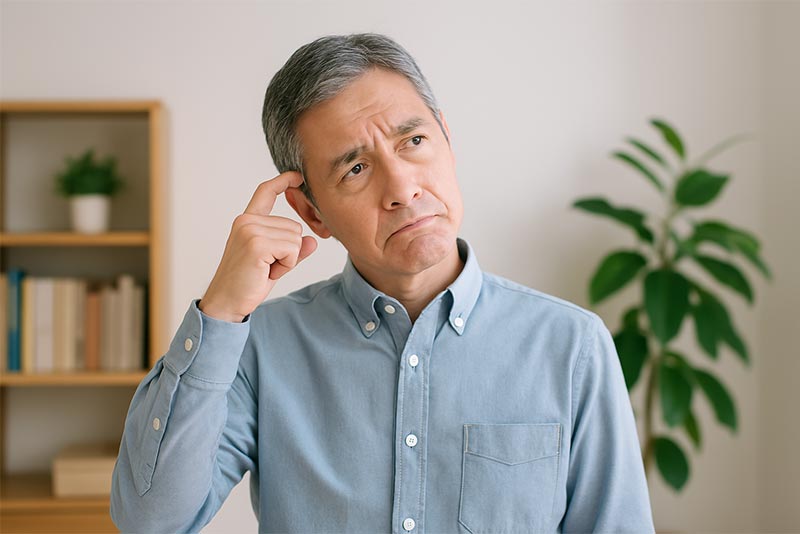
返礼品の所有権は寄附者本人にある
ふるさと納税の返礼品は、寄附を行った納税者本人の所有物と見なされます。
寄附によって生じる返礼品の権利は、寄附の名義人に帰属するため、家族が利用しても課税対象にはなりません。
たとえば、食料品や日用品などを家族と共有した場合には、家庭内消費の範囲と考えられ、贈与税の問題は生じません。
贈与税がかかるケース・かからないケースの違い
返礼品を高額かつ継続的に第三者へ提供した場合は、「贈与」とみなされる可能性があります。
たとえば、寄附者が自分の名義で寄附を行い、その返礼品を離れて暮らす親族や友人に頻繁に譲っている場合には注意が必要です。
その返礼品の評価額が年間110万円を超えると、受贈者に贈与税の申告義務が発生します。
参考:国税庁「贈与税がかかる場合」
税務署が着目するポイント
税務署は、贈与の「実態」に注目して判断を行います。
金額の大きさ、贈与の継続性、やりとりの記録があるかなどが審査の対象となります。
また、形式的には家族間の共有であっても、実質的な譲渡とみなされると課税対象になる場合があります。
ふだんから返礼品を本人が受け取り、自身で利用するのが基本です。
高額な返礼品を贈与した場合のリスクと対策

一時所得の対象となる可能性
ふるさと納税の返礼品は、一時所得として扱われることがあります。
一時所得の課税対象となるのは、同一年内に得た一時的収入の合計が50万円を超える部分です。
この金額を超えた場合には、確定申告が必要になります。
たとえば、寄附先の自治体が多数におよび、返礼品の合計評価額が大きくなった場合などが該当します。
参考:国税庁「一時所得」
贈与税の基礎控除を超える場合の申告義務
贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。
返礼品を第三者に贈与した場合、その価値が基礎控除を超えたと認められれば、贈与税の申告が必要となります。
とくに、意図的・継続的な贈与であり、証拠書類や明確な証言がある場合は課税対象になりやすくなります。
節度ある贈与のすすめ
返礼品の取扱いについては、税務上のリスクを回避するためにも、慎重な判断が求められます。
譲渡が必要な場合は、その理由や金額の記録を残しておくと安心です。
また、贈与に該当しない範囲での活用(例:家族内での共用)を心がけることで、不要な税務リスクを避けることができます。
親が子ども名義でふるさと納税をした場合の注意点

名義が誰かによって課税対象が変わる
ふるさと納税は、寄附を行った本人の所得税や住民税から控除される仕組みです。
親が子ども名義で寄附を行い、資金を負担した場合、形式上は子に対する贈与と判断されるおそれがあります。
この金額が基礎控除を超えれば、贈与税の対象となります。
税務署が確認する「実質的な負担者」
税務署は、「資金を実際に負担したのが誰か」に注目します。
たとえば、クレジットカードの決済名義や引き落とし口座が親である場合、たとえ子の名義で寄附していても「親が寄附した」と判断されます。
このような場合は、子ども側の寄附控除も認められず、税務上のリスクとなる可能性があります。
返礼品の扱いとトラブルを防ぐポイント

返礼品の譲渡は自己責任で
返礼品を譲渡した場合、それが無償であれば贈与とみなされる可能性があります。
たとえば、時計や家電など高価な返礼品を、第三者に意図的に譲った場合には注意が必要です。
実態が「贈与」と認定されれば、受贈者に課税義務が発生する可能性があります。
名義と受取先を一致させる
寄附者の名義と返礼品の受取人が異なる場合、税務上の疑義が生じます。
たとえば、会社員Aが寄附を行い、返礼品を両親の住所に送った場合、その受領者がA本人でないならば贈与と認定されるリスクがあります。
とくに高額返礼品では、受け渡しの経緯を明確にしておくことが大切です。
税務リスクを避けるための実務対応
以下のような対応を行うことで、税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。
- 寄附は本人名義で行い、返礼品も本人が受け取る
- 高額返礼品を第三者に譲る場合は、その理由と金額を記録する
- 領収書や受取記録、寄附履歴を保存しておく
贈与税との関係で気をつけたいふるさと納税のパターン
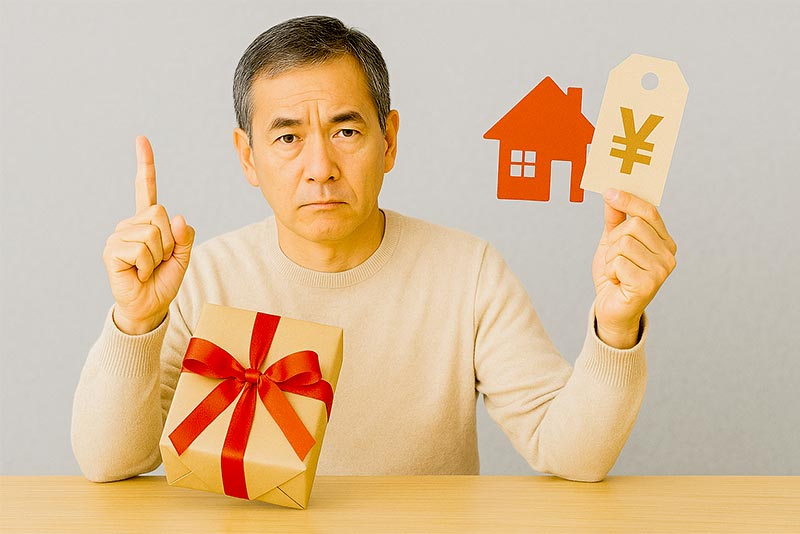
家族複数人で寄附を行うケース
家族それぞれが本人の名義で寄附し、各自が返礼品を受け取ることは問題ありません。
しかし、1人が複数名の分の寄附金をまとめて負担した場合には、名義人以外への贈与と判断される可能性があります。
この場合も、金額が年間110万円を超えると贈与税の申告対象になります。
法人・事業主による寄附と返礼品の私的利用
法人がふるさと納税を行い、返礼品を役員や従業員の私的用途に使用した場合には、法人から個人への「利益供与」と判断されるおそれがあります。
このような行為は、税務上の問題となる場合があり、個人側の課税や、法人の経費否認が発生するリスクがあります。
参考:国税庁「基本通達・法人税法」など関連通達
まとめ
ふるさと納税の返礼品は、寄附者本人に帰属するものです。
第三者へ譲渡する場合や名義と受取先が一致しないケースでは、贈与税や一時所得の対象となる可能性があります。とくに高額返礼品を扱う際は、税務署の判断基準や基礎控除額を踏まえたうえで、適切に運用することが重要です。
正しい知識をもとに、ふるさと納税を安心して活用しましょう。