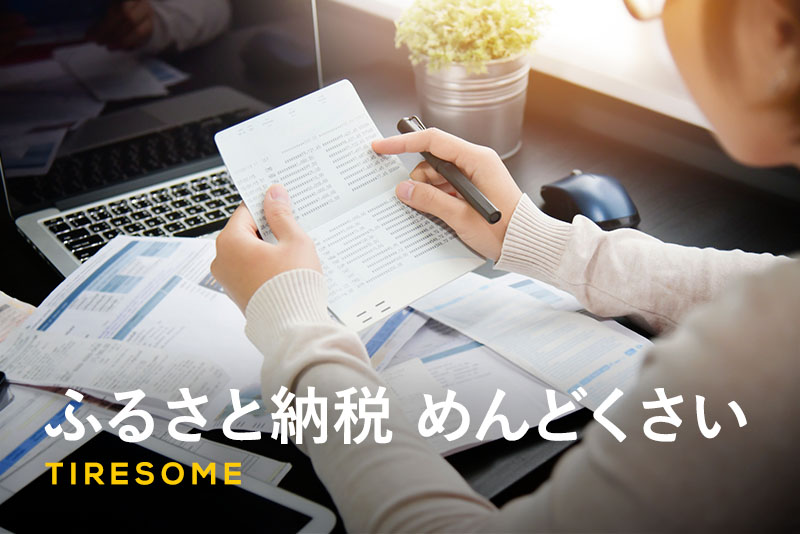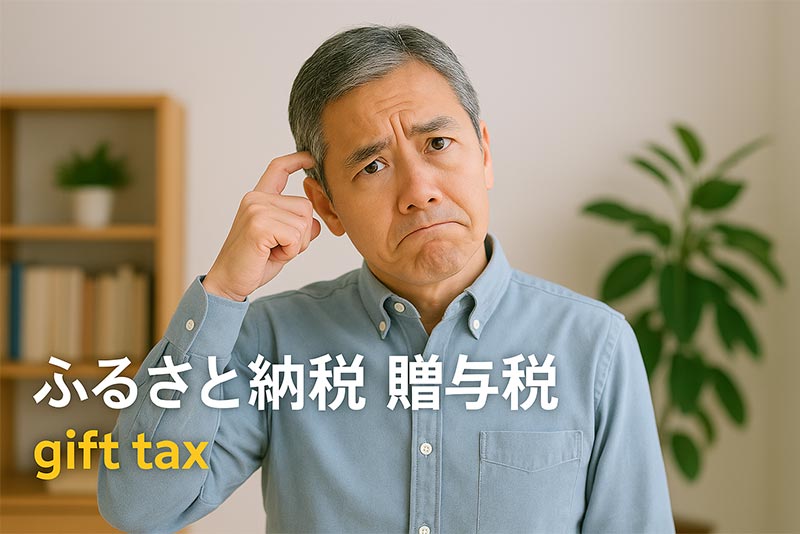目次
ヨーグルトに代表される発酵乳は、紀元前数千年という太古の時代に、偶然うまれたといわれています。
健康への効果が高く、味や食感もよいヨーグルトは、日本でも日常的に食べられている食品です。
この記事では、ヨーグルトに期待される主な効果を詳しく解説し、目的別の効果的な食べ方も紹介します。
ヨーグルトは乳酸菌によって作られる発酵食品

ヨーグルトは、牛乳などの原料に乳酸菌を加え、発酵させて作られる発酵食品です。
牛乳が主原料なので、たんぱく質やカルシウムなどの栄養素が豊富に含まれ、さらに乳酸菌による効果が期待できます。
乳酸菌とは?
乳酸菌とは、発酵によって糖を分解し、乳酸を作り出す微生物の総称です。
ヒトに対し有益な「善玉菌」であり、ヨーグルトのほか、チーズや漬物などの製造にも使用されます。
ヨーグルトの製造に使用される乳酸菌は、ブルガリクス菌、サーモフィルス菌、ガセリ菌、ビフィズス菌などが代表的です。
このうちビフィズス菌は、糖を分解する際に乳酸だけでなく酢酸も作るため、狭義の乳酸菌には含まれませんが、広義の乳酸菌に含まれます。
乳酸菌は種類ごとに特徴があり、どの乳酸菌を使用するかによってヨーグルトの効果が異なります。
現在はさまざまな種類の乳酸菌を使用したヨーグルトが販売されているので、求める効果に合った製品を選ぶとよいでしょう。
発酵食品とは?
発酵食品とは、微生物(細菌・酵母・カビ)の作用により元の食材が変化し、栄養価・風味・保存性などを向上させた食品です。
発酵は、微生物が作用して食材が変化するという点では腐敗と同じ現象ですが、ヒトにとって有益な場合は発酵、有害な場合は腐敗と呼ばれます。
日本で作られている主な発酵食品と、発酵に関わる微生物は以下のとおりです。
- ヨーグルト:乳酸菌
- チーズ:乳酸菌・カビなど
- 納豆:納豆菌
- 漬物:乳酸菌・酵母など
- 味噌・醤油・米酢:麹カビ・酵母・乳酸菌・酢酸菌など
- パン・ワイン・ビール:酵母
- 清酒:麹カビ・酵母
なお、ヨーグルトなどの発酵食品に含まれる、生きた善玉菌そのものを「プロバイオティクス」、食物繊維やオリゴ糖など、善玉菌の栄養源となる成分を「プレバイオティクス」といいます。
ヨーグルトに期待される健康効果

ヨーグルトにはさまざまな健康効果があり、その多くは乳酸発酵によるものです。
この章では、ヨーグルトに期待される健康効果を解説します。
腸内環境を整える
ヨーグルトの効果としてよく知られているのが、腸内環境の改善です。
ヒトの腸内には90兆〜250兆個の細菌が存在しており、細菌の性質によって「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つに分けられます。
- 善玉菌
人体に有益な細菌の総称。
乳酸菌やビフィズス菌などが代表的。
腸内で発酵し、乳酸や酢酸を発生させる。
悪玉菌の増殖を抑え、免疫力向上や生活習慣病予防などに効果的。 - 悪玉菌
人体に有害な細菌の総称。
ウェルシュ菌や一部の大腸菌などが該当。
腸内で腐敗を引き起こし、有害物質を発生させる。
悪玉菌が増えると、便秘や肌荒れ、食中毒や感染症のほか、さまざまな病気のリスクが高まる。 - 日和見菌
善玉でも悪玉でもない細菌の総称。
善玉菌が優勢のときは無害だが、悪玉菌が優勢になると悪玉菌と同様の働きをする。
腸内細菌のバランスは、善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割となるように保つのが理想的です。
善玉菌が増えた健康な腸内は、発酵により乳酸や酢酸が作られ弱酸性に保たれます。すると悪玉菌の増殖が抑えられ、腐敗や有害物質の産生を防げます。
毎日を健康に過ごすためには、ヨーグルトなどの発酵食品を摂取して善玉菌を増やし、腸内環境を整えることが大切です。
免疫力を向上させる
免疫細胞の約7割が存在する腸内の環境を改善することから、ヨーグルトには免疫力を向上させる効果もあります。
とくに、乳酸菌が分泌するEPS(菌体外多糖体)という物質が、免疫の向上に関わっています。
EPSには、異物の排除を担うNK(ナチュラルキラー)細胞を活性化させたり、インフルエンザなどのウイルス感染を抑制したりする作用が知られているのです。
例えば、ヒトを対象にしたある実験では、以下のような結果が得られています。
- 乳酸菌OLL1073R-1株で発酵させたヨーグルトを8週間以上毎日摂取すると、風邪への罹患リスクが低減した。
- この結果は、EPSによってNK細胞が活性化したためと推察されている。
内臓脂肪を減らす
ヨーグルトは、内臓脂肪の減少に効果的です。
これまでの多くの研究により、さまざまな種類の乳酸菌による体脂肪の減少作用が明らかになっています。
乳酸菌が分泌するEPSは、難消化性の多糖類であるため、消化管で消化吸収されずに大腸まで届き、腸内細菌のエサとなります。
この際に、脂肪の蓄積を抑えて肥満を予防する「短鎖脂肪酸」が産生されるのです。
EPSは短鎖脂肪酸の産生を促進するため、ヨーグルトなどで乳酸菌を摂取すると、体脂肪が減少すると考えられます。
例えば、ヒトを対象にしたある実験では、以下のような結果が得られています。
- 乳酸菌ガセリ菌SP株で発酵させたヨーグルト200gを12週間毎日摂取すると、内臓脂肪面積が平均4.6%減少した。
- この結果は、ガセリ菌SP株の摂取により、脂肪の吸収が抑制されるためと推察される。
血糖値・血圧の上昇を抑制する
ヨーグルトの摂取は、血糖値や血圧の上昇抑制にも効果があり、以下のような理由が考えられます。
- 血糖値の上昇抑制
ヨーグルトはGI値(血糖値の上がりやすさを示す指標)が低いため。
難消化性のEPSが食物繊維と同様の働きをし、糖の吸収を穏やかにするため。 - 血圧の上昇抑制
ヨーグルトには、血圧を下げる効果のあるカルシウムが含まれるため。
(カルシウムは不足時に、骨から供給されて血中濃度が高まるため、血管の収縮が起こり血圧が上昇。)
また、21か国の約15万人を対象とした大規模な追跡調査では、ヨーグルトを含む乳製品を摂取した集団で、2型糖尿病・高血圧・肥満のリスクが低下したと報告されています。
この研究結果の原因は特定されていませんが、乳製品に含まれる栄養素によるものではないかと推察されています。
コレステロール値を下げる
乳酸菌などの腸内細菌には、LDL(悪玉)コレステロール値を下げる効果があります。
コレステロールは、細胞膜・ホルモン・胆汁酸などの材料になる脂質の一種です。
腸内細菌が血中コレステロール値を下げる効果には、以下の理由が考えられます。
- 菌体がコレステロールに吸着し、排出を促すため。
- 菌体が胆汁酸に吸着して排出を促すため。
(排出された胆汁酸を補うためにコレステロールが消費され、結果として血中コレステロール値が下がる。) - 腸内細菌の代謝物である短鎖脂肪酸が、コレステロールの合成を抑制するため。
ヨーグルトのようなプロバイオティクスは、コレステロール値を下げるために有効です。
LDLコレステロール値が高い人は、飽和脂肪酸を多く含む動物性脂肪を控えた方がよいので、無脂肪や低脂肪のヨーグルトがおすすめです。
精神を安定させる
ヨーグルトには、セロトニンの材料となるトリプトファンが含まれ、精神を安定させる効果が期待できます。
- セロトニンとは
「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質。
セロトニンが低下すると、攻撃性が高まる、うつ状態になる、などの精神症状を引き起こしやすくなる。 - トリプトファンとは
体内で生合成できない必須アミノ酸のひとつ。
食事から摂り入れたトリプトファンは腸で吸収され、脳に移行して脳内セロトニンとなる。
また、体内におけるセロトニンの約9割が腸で作られており、腸の動きを活発にするなどの働きをします。
腸のセロトニンは脳に移行できないため脳内セロトニンにはなりませんが、腸と脳にはお互いに影響を及ぼし合う「脳腸相関」という関係があります。
ヨーグルトを摂取して腸内環境を整えると、トリプトファンが吸収されやすくなり、脳にもよい影響を及ぼすため、精神の安定に役立つのです。
目的別|ヨーグルトの効果的な食べ方

ヨーグルトには、目的に合った効果的な食べ方があります。
この章では、腸内環境の改善と血糖値の上昇抑制に効果的な食べ方と、1日の摂取量の目安を紹介します。
腸内環境の改善:オリゴ糖やバナナなどと一緒に食べる
腸内環境の改善には、ヨーグルトと一緒にオリゴ糖やバナナなどを食べると効果的です。
生きた善玉菌であるプロバイオティクスと、善玉菌のエサとなるプレバイオティクスの組み合わせをシンバイオティクスといい、より効果的に腸内環境を整えます。
プレバイオティクスにはオリゴ糖や食物繊維があり、オリゴ糖を含むはちみつ、食物繊維を含むバナナやリンゴなどのフルーツは、ヨーグルトとの相性がよく、おすすめです。
乳酸菌やビフィズス菌は胃酸により死滅しやすいため、生きたまま腸に届けるには、胃酸が薄まっている食後に摂取するとよいでしょう。
血糖値の上昇抑制:無糖ヨーグルトを食前に食べる
無糖のヨーグルトを食前に食べると、血糖値の上昇を抑制する効果が高まります。
前述のとおり、ヨーグルトの乳酸菌が分泌するEPSは、食物繊維と同様の働きをして糖の吸収を穏やかにするため、血糖値の急激な上昇を抑えます。
また、間食にも、低GI食品であるヨーグルトがおすすめです。
血糖値を上げないためには無糖ヨーグルトがよいですが、物足りない場合は、同じく低GI食品のリンゴやイチゴを加えるとよいでしょう。
1日100~200gを目安に毎日食べる
ヨーグルトは、1日100〜200gを目安に毎日食べると効果が持続します。
市販されているヨーグルトは、1パックあたり400g前後のものが多く、2〜4日で1パックの消費量です。
摂取量や価格の面でも、無理なく毎日の食生活に取り入れやすいヨーグルトですが、脂質が多いため、食べ過ぎないようにしましょう。
また、ヨーグルトは発酵の過程で乳糖が分解されているため、乳糖不耐症の人でも食べやすい乳製品です。
それでもお腹を壊しやすい場合は、40℃程度に温めるとよいでしょう。
まとめ
ヨーグルトの継続的な摂取は、腸内環境を整えることで、免疫力アップ・便秘改善・美肌効果・メンタルヘルス改善などの効果をもたらします。
ほかにも、ヨーグルトには、内臓脂肪の減少や血糖値・血圧・コレステロール値の上昇抑制といった作用があり、成人病予防にも効果的です。
腸内環境の改善には、プロバイオティクスであるヨーグルトと一緒に、オリゴ糖や食物繊維などのプレバイオティクスを摂取すると効果がアップします。
血糖値を下げたい場合は、食前に無糖ヨーグルトを食べるとよいでしょう。
ヨーグルトは、日常的に食べやすい食品であり、毎日100〜200gの摂取で効果が持続します。
ぜひ、毎日の食事に取り入れてみてください。