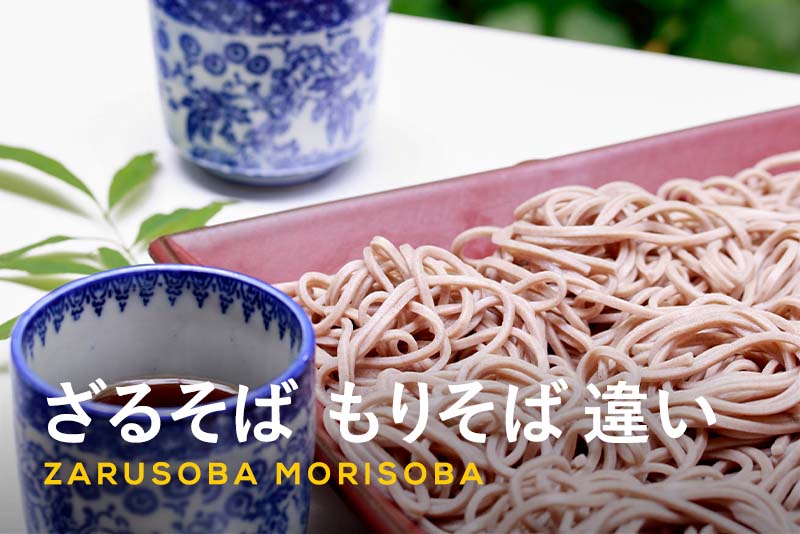目次
そば屋の定番メニューである「ざるそば」と「もりそば」は、見た目以上の違いがあることをご存じでしょうか?
「ざるそば」と「もりそば」には、海苔の有無だけでは語りつくせない違いや、そば屋の歴史が詰まっています。
呼び方の違いや歴史を知ることで、そばの魅力の奥深さを知りましょう!
ざるそばともりそばは何が違う?

諸説ありますが、お店によっても特徴が異なります。
生まれた歴史や経緯などの違いもありますが、見た目で判断できることも多いです。
現在でもよく見られる違いとしては、以下の相違点があります。
- 海苔の有無
- そばの量
- 提供される器
- つけ汁
- 薬味やトッピング
この中でも最も多いのが、「海苔の有無」です。
そば専門の飲食チェーンなどでも、もりは海苔が乗っていないもの、ざるには海苔が乗っているものとして、提供されています。
つゆや薬味などの「海苔の有無」以外の違いはないお店が多いです。
「もりそば」と並んで「おおもり」というメニューがあるように、そばの量でも差別化されています。
ざるそばに比べてもりそばの方が、そばの量が多いというお店も多いです。
また、提供される器、つけ汁、提供方法などの違いは、地域性や店主のブランディングにより生まれていったものもあります。
ざるそばともりそばの提供方法による違い
冷たいそばが提供される器として、ざるや四角いせいろが一般的です。
しかし、歴史によると、もともとは提供される器が異なっていました。
もりそばは、つけ汁をつけて食べる形で、汁をかけて食べる「かけそば」と区別するために生まれたメニューです。
もりそばは、茹でたそばをお椀状の器に盛り付け、つゆを別添えで提供されていました。
一方、ざるそばはもりそばのデメリットを解消するために考案されたメニューです。
当時の提供方法について諸説ありますが、ざるに盛り付けたそばと薬味のみで提供され、わさびや大根おろしなどとそばを一緒に味わうという食べ方だったといわれています。
ちなみに、もりそば、ざるそばと並ぶ「せいろそば」は、せいろに盛り付けられて、別添えのつゆと共に提供されます。
せいろそばとその他のそばとの違いは、器と海苔の有無です。
せいろそばは、一般的には四角い蒸籠(せいろ)に盛られて提供され、海苔はありません。
お店によって、つけ汁や薬味などが違うこともあります。
ざるそばが庶民に広まるうちに、四角いざる(またはせいろ)がざるそば、丸いざるに盛り付けられるのがもりそば、といった器の違いや付け合わせなどの提供方法の違いが生まれていったといわれています。
本来はつゆの味も違っていた
見た目だけでは判断できない点が、つけ汁の味付けです。
現在ではつけ汁や出汁汁は同じというお店が多く見られますが、ざるそばが生まれた当初はもりそばなどとは、味付けを変えた別のつゆを作って提供されていました。
ざるそばが生まれて以降、高級志向の人々に向けて、そばつゆの出汁には高級なかつお節を使用し、みりんを加えるなどして、より多くのコストをかけていました。
もりそばにはあっさりとしたつゆを提供し、ざるそばはそばの風味にも負けないようにしっかりとした旨みのある、コク深いそばつゆを作っているというお店もあります。
こうしたつゆの違いも、現代のそば屋ではほとんど見られません。
その理由として、ざるそばともりそばを差別化するために、つゆを分ける必要がなくなったといいます。
これには、生まれた時代背景が絡んできますが、当時高級品であったかつお節やみりんなどの食材が安定して供給されるようになり、食材の質も全体的に上がったことが理由の一つです。
もりそばが生まれた経緯

もりそばは江戸時代に生まれたそばの食べ方です。
そばの歴史として、それまではそば粉をまんじゅうのようにして食べる「そばがき」のスタイルでした。
そこから、そばを細切りにして食べる「そば切り」という形へと変化していきました。
そば切りには、現代と同じようにつけ汁につけて食べるのが一般的でしたが、時間のない人達がつけ汁をつけずに直接かけて食べる「かけそば」を食べるようになり、食べ方が二極化していったといわれています。
その時に、つけ汁で食べる形を「もりそば」、汁をかけて食べる形を「ぶっかけそば」と区別したことから、もりそばが考案されました。
現代では、もりそばにもざるが使われていたり、お店によっては区別されていなかったりする場合もあります。
もりそばとざるそばを見比べても、海苔が乗っているかどうかの違いのみというお店もありますが、つけ汁や薬味、麺の種類などを変えているお店もあります。
ざるそばが生まれたのは店主の知恵

では、ざるそばはどうして生まれたのでしょうか。
現代では、あまり違いはありませんが、これらの違いには生まれた経緯が関係しています。
ざるそばが考案されたのは、東京のとあるそば屋の店主がお客さんの悩みを解決するために編み出されたものでした。
それまで食べられてきた「もりそば」は、お椀のような入れ物にそばを盛るため、汁が溜まってしまい、食べ終わるまでにそばが汁を吸ってしまっておいしく食べられないと、悩んでいたといいます。
そこでそば屋の店主が思いついたのが、「ざる」です。
ざるに盛ることで、水が器に溜まることなく、最後までおいしく食べることができます。
もりそばと区別するべく名づけられたのが「ざるそば」ということです。
地域や年齢の差?呼び方の違い

ざるそばが生まれてからも、長く愛されてきたそばですが、時代や地域によっても違いがあるといいます。
全国へ広まるにつれて、地域独自の楽しみ方も増え、時代の移り変わりによる食文化の変化にも影響を受けていきました。
地域と年代による呼び方の違いを解説します。
東日本と西日本
関西などの西の方では、もりそばも「ざるそば」と呼ぶ人が多く、北海道や関東・甲信越では、区別して呼んでいるという人が過半数を占めているといわれています。
地域によって食文化も異なりますが、西日本ではそばよりもうどんの方がどちらかといえば主流です。
東日本側ではそばを多く食べる地域も多く、専門店の数も多く見られます。
若年層と年配層
年代によっても、呼び方が異なっています。これは、若年層と年配世代とで、そばのメニューに対する認識が違うことが理由の一つです。
若年層では総じてざるそばと呼び、年配層では区別して呼ぶ比率が多いといわれています。
ざるそばから生まれたご当地そば
そばが有名な地域では、「出雲そば」や「わんこそば」「へぎそば」などその地域の特産品や独自の進化を遂げたざるそばも数多く存在します。
というのも、そば切りの発祥とされるのが、そばの実の産地としても有名な信州です。
そば切りが信濃国の名物として、武将や大名へと知れ渡り、全国へと広まっていったといわれています。
全国へと広まり、各地で現地の人々に好まれる味や独自の文化を盛り込んだ、ご当地そばが誕生していきました。
現在、日本三大そばと呼ばれるのが岩手県の「わんこそば」、長野県の「戸隠そば」、島根県の「出雲そば」です。
これに加えて、幅広い麺が特徴的な東京都の「深大寺そば」、新潟県の「へぎそば」も有名です。
まとめ
もりそばとざるそばの違いとしては、海苔の有無ですが、その他にも地方や年代などによって呼び方が区別されてたり、総称としてざるそばと呼ばれていたりします。
もりそばとざるそばが誕生した経緯を知ることで、そばの歴史にも触れることができます。
ご自宅での茹で方を工夫すると、お店の味に近づけることができますので、ぜひお試しください。
参照:そばの「ざる」と「もり」の違いは? 老舗や専門家に「変遷」聞くと…|JCASTニュース
参照:必見!「ざるそば」と「もりそば」の明確な違いご存じですか?|出雲そば本田屋
参照:蕎麦のざる、もり、せいろの違いって?そば好き必見の解説|そば処更科
参照:長野県の信州そばとは?特徴や他のそばとの違いを解説!|有喜屋
参照:ざるそばともりそばの違い…オススメのそば屋の紹介|善ちゃんのサイエンスショー
参照:「もりそば」と「ざるそば」何が違う?【違いがわからん!】|毎日新聞
参照:もり・ざるの違い、信州そばの種類まで!奥深き<そばの世界>|acure
参照:海苔の有無だけじゃない? 「もりそば」と「ざるそば」の違い|東京ガス暮らし情報メディア ウチコト
参照:「もりそば」と「ざるそば」の違いとは?|TBS