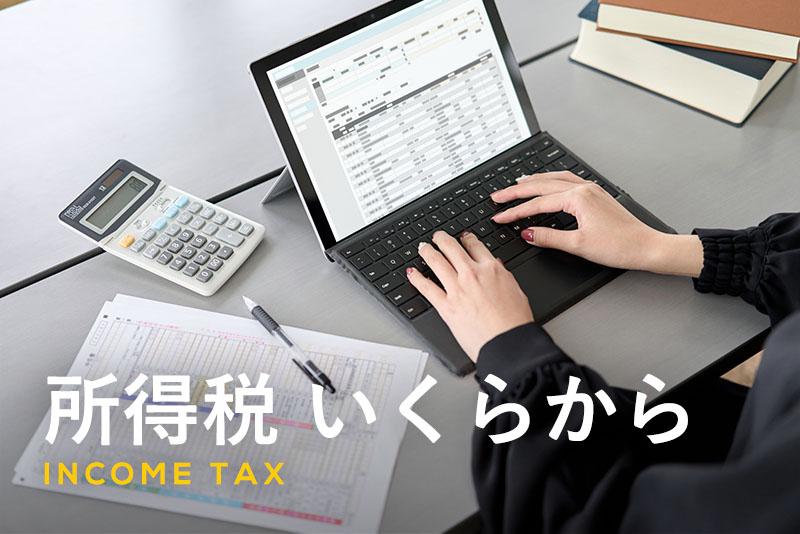ぶりには良質なたんぱく質や脂質・ビタミン類などのほか、EPAやDHAなど健康効果が期待される注目の栄養素がバランスよく含まれています。
ぶりの栄養を効果的にとるコツは、それぞれの栄養を効率よく補える食べ方を工夫することです。
この記事では、発育期の子どもや高齢者にもうれしいぶりの栄養素や効能、さらに効果的な食べ方や料理例についても紹介します。
新鮮でおいしいぶりの特徴や栄養成分

はじめに、ぶりの旬や鮮度・おいしさをチェックするポイント、主な栄養成分などを見てみましょう。
ぶりの特徴や旬
ぶりは日本近海に生息する回遊魚で、古くから「年取り魚」として神様に供えられるなど、伝統行事にも活用されてきました。
成長によって名前が変わる「出世魚」で、一般的に70㎝以上に成長したものがぶりと呼ばれます。
養殖のぶりは1年を通して店頭に並びますが、天然ぶりの旬は12月から3月ごろです。
なかでも12月から1月にかけて水揚げされる「寒ぶり」は身が引き締まり、脂がよくのっています。
養殖のぶりも脂がよくのっていますが、身は白っぽくやわらかめです。
新鮮・おいしいぶりの見分け方
切り身のぶりの鮮度や脂ののり具合を見分けるポイントを紹介します。
鮮度のよいぶりの特徴は以下の通りです。
- 皮にツヤがある
- 身に透明感がある
- 血合いが鮮やかな赤色をしている
- ドリップが出ていない
- 切り口がしっかりしている
脂ののり具合は、食べる人の好みや料理に応じて選び分けるとよいでしょう。
脂ののったぶりの特徴は以下の通りです。
- 身と皮の間に白っぽい脂の層がある
- 身に白く霜降り状の「サシ」が入っている
なお、ぶりの切り身は皮の色で、部位を確認できます。
- 背側:皮の色が深い緑色で、脂は少なめ
- 腹側:皮の色が白っぽく、脂がのっている
身そのものの旨味を重視するなら背側、脂がよくのったぶりが好みなら腹側がおすすめです。
ぶりの栄養成分
ぶりには子どもの発育や高齢者の健康維持に欠かせない栄養素がバランスよく含まれています。
ぶりに含まれる主な栄養素を一覧表で見てみましょう。
| 栄養成分 | 可食部100gあたりの 含有量 ※1 | 1日当たりの推奨摂取量 成人男性/成人女性 ※2 |
|---|---|---|
| エネルギー | 222kcal | 2600kcal/1950kcal |
| たんぱく質 | 21.4g | 65g/50g |
| 炭水化物 | 0.3g | 325~423g/244~317g |
| 脂質 | 17.6g | 58~87g/43~65g |
| ビタミンB1 | 0.23mg | 1.1mg/0.8mg |
| ビタミンB2 | 0.36mg | 1.6mg/1.2mg |
| ビタミンD | 8μg | 9.0μg/9.0μg |
| ビタミンE | 2mg | 6.5mg/5.0mg |
| カリウム | 380mg | 3000mg/2600mg |
| カルシウム | 5mg | 800mg/650mg |
| 鉄 | 1.3mg | 7.0mg/10.0mg |
出典 ※1:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 |文部科学省
※2:日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント|厚生労働省
18〜29歳の成人男性・成人女性(身体活動レベルⅡ(ふつう))の推奨量を記載。
ぶりには良質なたんぱく質と脂質が豊富に含まれています。
また、ビタミン類や鉄分などのミネラルの含有量も豊富です。
さらに、ぶりの脂質にはオメガ3脂肪酸など、体や脳の健康によいと話題の栄養素も含まれています。
ぶりの栄養素と効能|子どもや高齢者にうれしい健康効果

ここでは発育期の子どもや高齢者、エネルギー消費量の多い人などにうれしいぶりの栄養素とその効能について紹介します。
EPA|血液をサラサラにする
EPA(エイコサペンタエン酸)は体内では合成されないオメガ脂肪酸の一種で、ぶりなどの青魚に多く含まれます。
EPAには血流をよくする働きがあり、血管の詰まりや血圧上昇を防ぐのに役立つ栄養素です。
また、EPAにはアトピー性皮膚炎や花粉症を和らげたり、炎症を抑えたりする効果も期待できます。
DHA|脳を活性化する
DHA(ドコサヘキサエン酸)は、EPAと同じく青魚に多く含まれる脂肪酸の一種です。
DHAには、血流を改善して血栓ができるのを予防したり、コレステロール値や血圧上昇を抑えたりする効果が期待できます。
また、DHAは脳を活性化することで記憶力や学習能力の向上に役立つため、子どもから認知機能の低下を予防したい高齢者まで積極的にとりたい栄養素です。
DHAもEPAと同じく体内では合成されないため、青魚やサプリでとる必要があります。
献立にぶりを取り入れることで、DHAやEPAをはじめとした栄養素を一度の食事で効率よく補うことができるでしょう。
ビタミンB1|疲労回復に役立つ
ぶりに含まれるビタミンのうち、水溶性のビタミンB1は糖質をエネルギーに変える際に必要な栄養素です。
ビタミンB1が不足すると、糖質からエネルギーを効率よくつくることができず、細胞に必要なエネルギーが不足するため、疲れやすくなります。
ビタミンB1が「疲労回復ビタミン」と呼ばれるのはこのためです。
また、ビタミンB1には、糖質を栄養源とする脳や神経を正常に保つ効果もあります。
ビタミンB2|体の発育を助ける
ぶりに含まれる水溶性のビタミンB2は、糖質・脂質・タンパク質の代謝やエネルギー生産に欠かせない栄養素です。
とくに、皮膚や粘膜、髪や爪などの細胞を再生させる働きや、体の成長を促す働きがあるため「発育のビタミン」とも呼ばれます。
発育期の子どもはもちろん、スポーツをする人やダイエット中の人、妊娠中や授乳中の人にもビタミンB2は欠かせません。
日々の食事にぶりを上手に取り入れてみましょう。
ビタミンD|骨や歯の健康維持に役立つ
ぶりにはカルシウムはそれほど多く含まれていませんが、カルシウムの吸収を助ける脂溶性のビタミンDが豊富です。
ぶり一切れ(約100g)を食べると、ビタミンDの一日の推奨摂取量をほぼカバーできます。
そのため、ぶりはカルシウムが豊富な食品と相性がよく、一緒に食べると骨や歯の成長や骨粗しょう症の予防に効果的です。
また、ビタミンDは免疫力の向上に役立つため、風邪やインフルエンザの予防、アレルギー症状を和らげる効果も期待できるでしょう。
ビタミンE|老化や動脈硬化の予防に役立つ
脂溶性のビタミンB1は強い抗酸化作用を持ち、細胞の老化や病気を予防するのに役立つ栄養素です。
シミやしわの原因となる活性酸素の増えすぎを抑える効果が期待できるため、「若返りのビタミン」とも呼ばれます。
また、悪玉コレステロールの増加を抑えるため、動脈硬化の予防にも効果的です。
タウリン|肝機能を高める
タウリンは、牡蠣やサザエなどの貝類やイカ・タコ、魚の血合いに多く含まれる水溶性のアミノ酸の一種です。
ぶりの血合いにもタウリンが豊富で、身体の疲労を和らげるほか、肝機能を高める効果が期待できます。
また、血液中の中性脂肪やコレステロールを減らす働きがあるため、動脈硬化や心疾患などの予防にも効果的です。
ぶりの栄養を効果的にとれる食べ方

ぶりの栄養を無駄なく上手に摂取できる、おすすめの食べ方や食品の組み合わせ例、料理法などを紹介します。
生で食べる
EPAやDHAは酸化しやすく、加熱によって流出しやすいため、ぶりを生で食べると希少な栄養を無駄なく摂取できます。
おすすめ料理例は以下の通りです。
- 刺身
- 刺身サラダ
- カルパッチョ
- にぎり寿司
- 漬け丼
脂が気になる人は、ぶりしゃぶにすることで余分な脂を落とすことができます。
ただし、火の通しすぎには注意しましょう。
煮汁と一緒に食べる
ぶりに含まれる水溶性のビタミン類B1やB2、タウリンなどは、煮汁も一緒に食べると無駄なく摂取できます。
おすすめ料理例は以下の通りです。
- ぶりの煮つけ
- ぶりのトマト煮込み
- ぶり大根
- 味噌汁やスープ
- ぶり茶漬け
定番はぶり大根や煮つけなどの和食ですが、スープや洋風のアレンジを加えることで、献立の幅がさらに広がります。
糖質を含む食品を組み合わせる
ぶりのビタミンB1は糖質を効率よくエネルギーに変換するため、炭水化物など糖質を含む食べ物と相性が抜群です。
スポーツをする人や活動量の多い人などは、ぶりと炭水化物を一緒に食べることで、スムーズな疲労の回復が期待できるでしょう。
おすすめの組み合わせ例は以下の通りです。
- ぶり+ご飯
- ぶり+パスタ
- ぶり+パン
定番はご飯との組み合わせですが、照り焼きバーガーなどにアレンジすると子どもにも喜ばれ、運動の合間にも食べやすいでしょう。
カルシウムを含む食品を組み合わせる
ビタミンDが豊富なぶりは、カルシウムを含む食品と一緒に食べるのがおすすめです。
ビタミンDの働きにより、そのままでは体内に吸収されにくいカルシウムの吸収率がアップします。
おすすめの組み合わせ例は以下の通りです。
- ぶり+乳製品
- ぶり+豆・豆製品
- ぶり+緑黄色野菜
定番おかずのぶりの照り焼きや塩焼きに小松菜やほうれん草のお浸しや煮豆を添えたり、味噌汁やシチューをプラスすると、カルシウムを効率よくとれます。
味つけを変えて、味噌煮やクリーム煮にアレンジするのもよいでしょう。
まとめ
ぶりは、EPAやDHA、ビタミン類、たんぱく質など、健康維持に欠かせない栄養素をバランスよく含む食品です。
子どもの発育や高齢者の健康維持にも効果が期待できるため、日々の食卓にぜひ取り入れてみてください。
おすすめの食べ方や食材の組み合わせ例も参考に、ぶりの栄養を逃さず効率よく摂取しましょう。