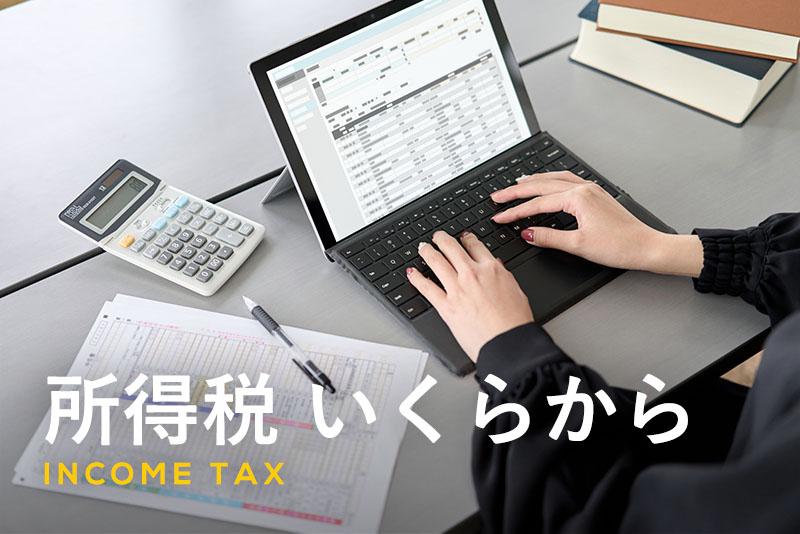目次
いんげん(さやいんげん)は、豆が未熟なうちに緑の若ざやごと食べる、夏が旬の野菜です。
いんげんには、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれます。
この記事では、いんげんの栄養と健康効果をわかりやすく解説します。
いんげんの栄養を逃さないゆで方や調理のコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
いんげんに含まれる主な栄養素一覧

以下に、いんげんに含まれる主な栄養素の含有量をまとめます。
| 栄養素 | いんげん(ゆで) 可食部100g当たり含有量 |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 食物繊維 | 3.9g |
| カリウム | 270mg |
| カルシウム | 53mg |
| マグネシウム | 22mg |
| 鉄 | 0.7mg |
| β-カロテン | 500μg |
| ビタミンK | 51μg |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| 葉酸 | 53μg |
| ビタミンC | 6mg |
なお、一般的な大きさのいんげん100gは、15〜20本ほどです。
いんげんの栄養による健康効果

この章では、いんげんの栄養による健康への効果を解説します。
β-カロテン・ビタミンC|肌の老化を防ぐ
いんげんに含まれるβ-カロテンやビタミンCには強い抗酸化作用があり、肌の老化防止に効果的です。
また、細胞の再生を促すビタミンB2も含まれ、肌の健康維持に役立ちます。
β-カロテン、ビタミンC、ビタミンB2には、以下のような特徴や肌への効果があります。
- β-カロテン
緑黄色野菜に多く含まれるカロテノイド色素。
体内で必要な分だけビタミンAに変換される「プロビタミンA」の代表格。
抗酸化作用があり、シミ・シワ・たるみなどの肌の老化を防ぐ。 - ビタミンC
強い抗酸化作用をもつ。
コラーゲンの生成に必須の栄養素で、肌のハリや弾力を保つ。 - ビタミンB2
皮膚や粘膜などの細胞の再生に関わり、肌を健康に保つ。
不足すると、肌荒れ・口角炎・口内炎などを引き起こす。
食物繊維|腸内環境を改善する
いんげんは、腸内環境の改善に役立つ食物繊維が豊富です。
腸内環境が改善すると、以下のような健康効果が期待できます。
- 便秘や下痢の改善
- 肌荒れの予防
- 免疫機能の維持
- 生活習慣病の予防
食物繊維は「ヒトの消化酵素で消化されない難消化性成分の総体」と定義され、大きく水溶性と不溶性の2種類に分類できます。
※文部科学省「成分表における食物繊維の分析法の変更について」(PDF)
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維には以下のような性質・効果があります。
- 水溶性食物繊維
水に溶け、水分を吸収してゲル化する。
腸内細菌のエサとなり善玉菌を増やす。 - 不溶性食物繊維
水に溶けず、水分を吸収して膨らむ。
腸内の有害物質を吸着し、排出する。
善玉菌のエサとなり腸内環境を改善する。
いんげんには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がバランスよく含まれます。
カリウム|むくみや高血圧を予防する
いんげんに含まれるカリウムは、むくみや高血圧の予防に効果的です。
むくみや高血圧の原因のひとつに、塩分(ナトリウム)の摂りすぎが挙げられます。
体内のナトリウム濃度が高くなると、それを下げるために組織の水分量が増え、むくみが生じます。
同様に、血液中のナトリウム濃度が高くなると、血管内の水分が増えて血液量が増し、血圧が上がるのです。
カリウムには、余分なナトリウムの排出を促し、細胞内の浸透圧を一定に保つ働きがあります。
また、いんげんに含まれるカルシウムとマグネシウムも、高血圧の予防に役立ちます。
カルシウムとマグネシウムの不足は、高血圧の原因のひとつです。
カリウム・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルが豊富ないんげんは、むくみや高血圧を予防する効果が期待できます。
ビタミンB1・アスパラギン酸|疲労の回復を助ける
いんげんに含まれるビタミンB1とアスパラギン酸は、疲労の回復を助ける栄養成分で、以下のような働きがあります。
- ビタミンB1
糖質のエネルギー代謝を高めて疲労を回復させる。 - アスパラギン酸
疲労の原因となる血中アンモニアの解毒を助け、疲労の軽減に役立つ。
生のいんげんには、アスパラギン酸が320mg/100g含まれる。
※参考:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
ビタミンB1やアスパラギン酸の働きにより、いんげんには、疲労回復を助ける効果が期待できます。
葉酸・鉄|貧血を予防する
いんげんに含まれる葉酸と鉄は、以下のような働きで貧血を予防します。
- 葉酸
ビタミンB12とともに赤血球の生成に関わり、造血を促す。
不足すると、動悸・倦怠感・めまいなどの症状を伴う巨赤芽球性貧血を引き起こす。 - 鉄
赤血球に含まれるヘモグロビンの材料となる。
不足すると、疲労感や血色不良などの症状を伴う鉄欠乏性貧血を引き起こす。
また、葉酸は、ビタミンB12とともにDNAの合成に関わり、細胞の増殖が盛んな胎児や乳幼児にも重要な栄養素です。
このため、妊婦や授乳婦には葉酸の十分な摂取が推奨されています。
ビタミンK|骨の健康を維持する
いんげんに含まれるビタミンKは、骨の健康維持に関わる栄養素です。
ビタミンKは油に溶けやすい脂溶性ビタミンで、骨に存在するたんぱく質「オステオカルシン」を活性化します。
オステオカルシンはカルシウムと結合し、骨を石灰化して強度を保ちます。
骨の健康維持のほかにも、ビタミンKには出血時に血液の凝固を助ける働きもあります。
ビタミンKが不足すると、骨粗しょう症のリスクが高まったり、出血しやすくなったりするので注意が必要です。
いんげんの栄養を逃さない食べ方

いんげんには、健康効果のあるさまざまな栄養素が含まれます。
この章では、いんげんの栄養を逃さない食べ方を紹介します。
90秒を目安にゆでる
いんげんは、90秒を目安にゆでると、栄養成分の流出を抑えられます。
いんげんの栄養を逃さずにゆでる手順は以下のとおりです。
- いんげんを洗ってヘタを切り落とし、すじがあれば取り除く。
- まな板にいんげんを並べ、塩を振ってから手で転がす。(板ずり)
- 沸騰したお湯に2.のいんげんを加え、90秒程度ゆでる。
※板ずりの工程を省く場合は、塩を加えたお湯でゆでる。 - ザルにあげて氷水にさらし、キッチンペーパーなどで水分を拭き取る。
板ずりをしたり、氷水で素早く冷やしたりすると、いんげんが色鮮やかにゆで上がります。
蒸しゆで・電子レンジを利用する
蒸しゆでや電子レンジの利用で、いんげんに含まれる栄養素の流出を抑えられます。
なお、いんげんの下処理は、前述した「いんげんの栄養を逃さずにゆでる手順」の1と2の工程を参照してください。
蒸しゆでの手順
- いんげんを下処理する。
- フライパンにいんげんを並べ、少量の水を加える。
※いんげん100g(15〜20本)に対して水50mLが目安。 - フライパンにふたをして火にかけ、沸騰してからさらに90秒ほど加熱する。
- ザルにあげて氷水にさらし、水分をよく拭き取る。
電子レンジ加熱の手順
- 下処理したいんげんを耐熱皿に並べ、ラップをかける。
- 600Wの電子レンジで90秒ほど加熱する。
- 氷水にさらして冷やし、水分をよく拭き取る。
油で調理する(炒める・揚げる)
いんげんは、油で調理すると、脂溶性であるβ-カロテンやビタミンKの吸収率が高まります。
洗ってヘタやすじを取ったいんげんは、水分をよく拭き取ってから、炒めたり揚げたりしましょう。
生のいんげんを炒めるときは、途中で少量の水を加えてふたをし、炒め蒸しにすると早く火が通ります。
煮汁ごといただく
いんげんを柔らかく食べたい場合は、煮物にして煮汁ごといただくと、流出した栄養素を逃さず摂取できます。
みりん・しょうゆなどを加えただし汁に、いんげんを加えて柔らかくなるまで煮込みましょう。
油揚げや厚揚げを加えると、ボリュームのあるおかずになります。
煮汁もいただくので、だし汁の量を少なめにし、薄味で煮込むのがポイントです。
柔らかく煮ると、小さい子どもやお年寄りも食べやすく、また、歯ごたえのあるいんげんとは違うおいしさが味わえます。
まとめ
いんげんに含まれる栄養素と健康効果は次のとおりです。
- β-カロテン・ビタミンC
強い抗酸化作用で肌の老化を防ぐ。 - 食物繊維
腸内細菌のエサとなって善玉菌を増やし、腸内環境を改善する。 - カリウム
余分な塩分の排出を促し、むくみや高血圧を予防する。 - ビタミンB1・アスパラギン酸
エネルギー代謝を高めて疲労の回復を助ける。 - 葉酸・鉄
巨赤芽球性貧血や鉄欠乏性貧血を防ぐ。 - ビタミンK
骨の強度を保つたんぱく質を活性化し、骨の健康を維持する。
いんげんには、健康によい栄養成分が豊富に含まれます。
夏に旬を迎えるいんげんを、ぜひ食卓に取り入れてみてください。